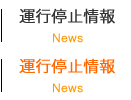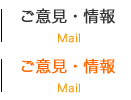Narrow Gauge Railways in China
& Taiwan
| 台湾 訪問リスト >> 新平渓煤砿 >> 2025.1 |
| 新平渓煤砿 Xinpingxi Coal Mine Museum 2025.1.11 |
||
| レポート : 【 2025.1 】 |
||
この施設を初めて訪れたのは 2024年の11月でしたが、平日のためか 見学客の来訪が少なく、列車が僅かしか走りませんでした。 博物園区の女性スタッフから、「休日なら 来訪者も多く 列車も頻繁に走りますよ」 と言われたため、翌年1月の土曜日に再訪することにしました。 (*印:2024.11.15 撮影の写真です) |
||||||||
 |
土曜の朝 9時過ぎに 期待して現地入りしましたが、この日も 午前中は来場者が少なく、”独眼小僧”が 姿を現したのは 11時を回ってからでした。 写真は、10人近くの乗客を乗せて 博物園区の外に出てきたところです。 6両の客車を曳いています。 |
|
 |
列車は、しばらくの間 道路に沿って進みます。 女性運転士のコスチュームは、石炭列車が走っていた頃に合わせた演出で、当時の様子を偲ぶことができます。 ところどころに 架線柱が残っていて、以前は電化軌道であったことがわかります。 |
|
 |
終点の月台公園に到着すると、下車した運転士が機関車を 切り離しました。 | |
 |
終点には 機回し線が設けられており、機関車の付替え作業が行なわれます(2024.11 撮影)。 | |
 |
上の写真の続きです(2024.11 撮影)。 間もなく 客車と連結です。 |
|
 |
連結作業が終わったところです(*)。 機回し作業が行われている間、乗客達は 石炭の搬出中継地であった頃の遺構などを見学しています。 |
|
 |
月台公園を出たところで、戻りの列車を待ち受けました。 ここで 池の端を通ります。 |
|
 |
上の写真の続きです。 眼の前を 機関車が通過していきます。 ”ニチユ”のエンブレムが誇らしげですね。 この後は、道路に駆け上がって 列車を追いかけます。 |
|
 |
博物園区まであと少しという所で 列車に追いつき、道路から 再び撮ることができました。 |
|
 |
こちらは、博物園区に ”独眼小僧”が戻ってきたところです(*)。 背後の大屋根の建物は 車庫 と 坑口 を兼ねています。 庫内には ”独眼小僧”の 予備機の姿も見えています。 |
|
 |
その坑口から外を眺めたところです(*)。 車庫の周りには 各種資料の展示施設があります。 坑内には 入れませんでした。 |
|
 |
なお 見学客が少ない時間帯には、”独眼小僧”ではなく 2両の客車を連結した 小型のバッテリー機関車が登場します(*)。 写真は 博物園区を出て 月台公園に向かうところですが、編成が短いためか 推進運転で進んでいきました。 |
|
 |
途中で橋の下を通り抜け、推進運転で進んでいきます。 | |
 |
後を追って 月台公園へ向かうと、先ほどの列車が 停車していました(*)。 戻っていく際の機回し作業が要らないため、女性運転士は 車内で待機しています。 |
|
 |
月台公園には、かつて石炭の搬出中継地であった頃の引込線が、今も残っています。 | |
 |
その廃線跡は、2連のチップラーを擁するチップラー小屋へと 続いていました。 ここで降ろされた石炭は、ベルトコンベアを介して下にある 選炭・積替施設へと運ばれていたようです。 |
|
 |
ベルトコンベア跡に沿って坂道を降りて行くと、選炭施設と積替施設の遺構が残されていました。 写真の廃線跡は、台湾鉄路の引込線です(軌間 1,067mm)。 なお 右奥に立派な道路橋が見えますが、先ほどの月台公園は その裏側に位置します。 |
|
 |
【参考写真】 炭砿 操業中の1990年代に、英国の John Raby 氏が撮影した 石炭列車です(了承いただき掲載)。 これらは 当時の 電化軌道や機関車の様子がわかる貴重な写真です。 |
|
 |
This photo shows the back of the loco. この写真で 機関車後部の様子がわかります。 |
|
 |
In this one the NiChiYu makers name is clearly visible in Katakana. こちらの写真では、片仮名で記された”ニチユ”のメーカー名をはっきり見ることができます。 |
|